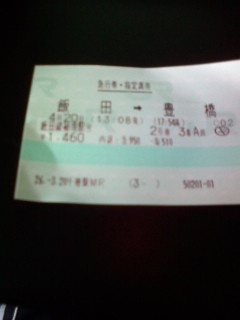「伝わるってナンだ? 情報保障から考える」の2回目です。2回目は、“障害のある人と情報保障”を対談形式で考えていきます。
Chabin(以下、C):
よろしくお願いします。まず、自己紹介をお願いします。
ヨッシー(以下、ヨ):
名古屋市に住んでいますヨッシーです。現在は、名古屋盲人情報文化センターで点字出版の仕事をしています。今回、大学時代から今までを振り返る良い機会になればと思います。よろしくお願いします。
点字出版って・・・
C:
点字出版って何をやるのですか。
ヨ:
えっと広報や各種お知らせなど、自治体や企業からの点字版の受託物制作、新刊本の発行やら、 点字名刺、案内板などの点字サインの監修、 UV加工など。
C:
やることおおいですねえ。 点字サインにJIS規格があるとか聞いたことあるんだけど・・・。
ヨ:
2006(平成18)年に、公共施設や設備における点字の表示原則や表示方法について定めたJIS規格「高齢者・障害者配慮設計指針―点字の表示原則及び点字表示方法―」が公表された。2000年には、点字ブロックの標準化(JIS規格化)が公表されたかな。2002年に社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会が公表した「視覚障害者の安全で円滑な行動を支援するための点字表示等に関するガイドライン」って本は手元にあって読んでいる。
C:
それ、気になるかも。何が書いてあるの?
ヨ:
案内板の中の階段や改札口などのサインはこの記号を仕えとか、凡例は左上とか・・・。
点字に関する資格
C:
点字に関する資格があるとか?
ヨ:
点字技能師か。 点字指導員もあるかな。
C:
どういう資格?
ヨ:
点字に関する卓越した知識・技術を有する方に対して資格を付与することにより、点字関係職種の専門性と社会的認知度を高め、合わせて点字の普及と点字の質の向上を図り、視覚障害者に的確な情報を提供することを目的とする。点字指導員は事前課題と3日間の講習と最後に試験に受かれば認定されるよ。
読み上げ機能があるけど・・・
C:
今パソコンとかケータイとかの読み上げ機能とかあるけど、そんな中でも点字にする意義ってどこにあると?
ヨ:
やっぱり音声だと受動的な情報入手になるから聞き流すならいいけど頭に入りにくい。 勉強や本を読むなら、点字が理想。すぐ戻って確認できたり、読みたいところにすぐいけたり、自分のペースで読み進めることができる。人の名前とか聞きにくい言葉は、間違えて聴いて覚えてしまうこともあるし、点字なら確実。まあ音声も好きだけどね。点字を読むより、聴くほうが速度的に早く読めるからたくさん情報をしれた気になるし。まあ理想をいえば全部点字で読みたいけど、点字はかさばってしょうがない。
C:
大学の数学だけは手書きでノートしていたな。 パソコンだと頭にはいらない気がして。 数式をパソコンで書く方法もあるけど。
ヨ:
自分も数学は帰ってから点字で打ち直したりしていたな。
対談後記
少し、gdgd感が残りました。今回は、視覚障害・点字に焦点を当てました。点字の世界は本当に奥深そうです。最後もちらっと出てきましたが、この時はこの方法で、あの時はあの方法でと、その時々でやり方を変えることで広がる世界はとてつもなく大きいです。
この「伝わるってナンだ? 情報保障から考える」は毎月第3木曜の夕方に更新していきます。次回は、在日外国人と情報保障について対談形式で考えていきます。